2018年10月6日、83年間もの間、日本の水産物の集まる場所として使われてきた築地中央卸売市場が移転のため、幕を閉じました。
移転先は豊洲。移転が決まってから、様々な人たちからの反対があり、また、移転先の土地の安全性への問題も持ち上がりました。多くの問題がある中これからどうなることかと、都民ならず日本中の人たちが見守ってきたことでしょう。
長く愛されてきた築地市場。なぜ移転が必要だったのか?

あなたは築地が今、どうして移転の必要が出てきたのかご存知ですか?
築地市場は83年間も使われてきた場所ではあるけれど、年々水産物の水揚げ量が増えた今、手狭になってきたのです。
また、何しろ古すぎて、老朽化した市場の建物は危険。いつ事故が起こっても仕方がない状況だったとか。
長く使い続けていると、まだ使えているからと、なかなか新しいものに切り替えられません。
私自身、使い慣れたものの方に愛着を感じたり、新しいものは使いにくいんじゃないかと尻込みします。
けれども83年間といえば昭和と平成の大部分です。
これからの時代のことを考えると、必要なことだったのかな〜と思います。
築地市場が閉鎖となった翌日のターレ大移動

テレビのニュースで見たのですが、築地で働いていた人たちが、ターレと呼ばれる運搬用の特殊なトラックに乗って、列をなして豊洲へと向かっていました。
ターレが群れをなして移動していく様子は、今までも、そしてこれからも目にすることはないであろう壮観な光景です。
永年働いた職場を移るというのは、ものすごく感慨深いのだろうな〜。ターレに乗っている人が皆、左手の築地の方を眺めるのがとても印象的でした。おそらく、市場で働く方々には色々な思いがあったことでしょう。
私たちが毎日食べている魚や、果物、漬物は、この人たちが働いてくれていたおかげだったんだな、としみじみ思いました。
ニュースの最後にインタビューされていた青年の言葉が忘れらない
最後の方に青年がインタビューを受けていました。
彼は築地で働き始めてまだ数ヶ月。
でも、この仕事を愛しています。
築地と豊洲についての感想を求められた彼は、こう話します。
「築地には、この仕事に情熱を注いで働いているような、そんな景色が毎日ある。一方、豊洲は、きれいな箱で、冷蔵庫ときれいな店舗が並んでいるだけのところ。自分たちには、新たな市場である豊洲に活気や思いを持っていくという使命がある。」
活きのいい水産物や農産物を買い入れる、あるいは売る…。
この仕事に私はとてつもないロマンを感じました。
築地市場の終幕と豊洲市場の誕生

今、世界はグローバルとなり、文明の利器のおかげで、魚を獲ることも輸送することも、昔とは格段の進化を遂げました。けれど、市場で働く人たちの心意気は、江戸時代の頃と変わらず熱いのかもしれません。
築地市場の終幕と豊洲市場の誕生という、歴史的事件に立ち会えた私たちは、とてもラッキーだったと思うのです。
インタビューの青年のような人たちが市場で働いてくれている限り、日本の産業は大丈夫だな〜と頼もしく思ったのでした。
毎日の食卓にのる食材に感謝の気持ちを。



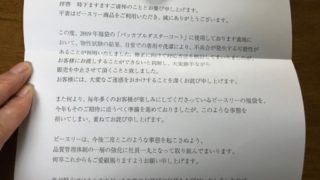





















コメント