今しみじみ思う、本当は必要なかったもの
本当は必要のなかったものが、今まで色々ありました。
特に大きく不要だったもの…それは、私の嫁入り道具。
全てが不要というわけではありません。
要らなかったと思えるのは、和箪笥、ドレッサー(三面鏡)、下駄箱。
和服を着ることなどほとんど無い!しかもひとりでは着られない!そんな私には必要ない!
和箪笥には、私の嫁入り前に作ってもらった、着物が何着かと、和装小物一式が入っています。でも、狭い新居に置く場所がなかったので、夫の田舎の実家に置いたまま、今日まできてしまいました。
下駄箱も同様です。東京の新居には小さな作り付けの下駄箱がありました。
ちょっぴり私の憧れだった三面鏡
三面鏡って、化粧品を収納したり、ドライヤーやヘアスプレーを収納したりしますよね?
最初の何年かは重宝した記憶があります。
が、そのうち子どもが生まれると、とても鏡台の前に座るような優雅な時間は持てなくなり、いつしか、朝のお化粧や夜の顔の手入れは洗面台で行うように……。
使わないものが部屋の片隅にあることが嫌でたまらなかった私は、鏡台を粗大ゴミに出しました。
昔の嫁入り道具は、今の時代にそぐわない
おそらく昔の嫁入り道具は、昔の田舎の広い家で使われるものだったのでしょう。
けれども、私の両親も私自身も、そのことに考えが到らなかったのです。
鏡台の処分は親に申し訳なかったのですが、とにかく東京のマンション生活には不要でした。
これだけは私が望んだはずが…
結局今、持て余しています。おひな様。
私の田舎では、女の子が誕生すると、母親の実家からおひな様を贈る習わしとなっています。
私が子どもの時、うちにはありませんでした。
母親の実家が経済的に苦しかったからです。
そのため、私はおひな様に憧れていたのでしょう。
娘が産まれた時、実家から贈ってもらえることになり、私は「7段飾りのおひな様が欲しい!」と言ってしまったのです。
田舎の風習はさらに奇異だった!
昔の田舎の風習は、とても変わったものでした。
嫁入り道具にしても、お雛様にしても、それらは全て一旦夫の実家(つまり私の嫁ぎ先)に送られ、それらを皆で1度確認し、それから私達の元に届くのです。
なんと手間なんだろうと当時は思っただけでしたが、後に私はあることに気づきました。昔は家と家との結婚だったから、面倒でも1度婚家を通したのではないか?
それともうひとつ、夫の両親達に、これこれの物をうちは用意しましたよ、と念を押す意味もあったのではないか。
もっと下世話な見方をすれば、親の見栄もあったかもしれません。

本当に面倒臭かった、昔の習わし
その点現代は、純粋に人と人との結婚のような気がします。
私の両親が散財をして私のために誂えてくれた、数々の道具。
それらを不要なものと決めつけるのはかなり良心が痛みます。
でも、今の私の生活を快適にするためにも、天国の両親に許してほしいなと思うのです。
手放してしまって後悔しているものバージョンも書きました。













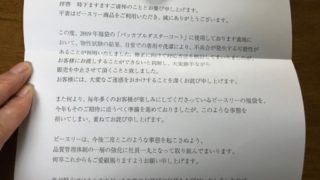







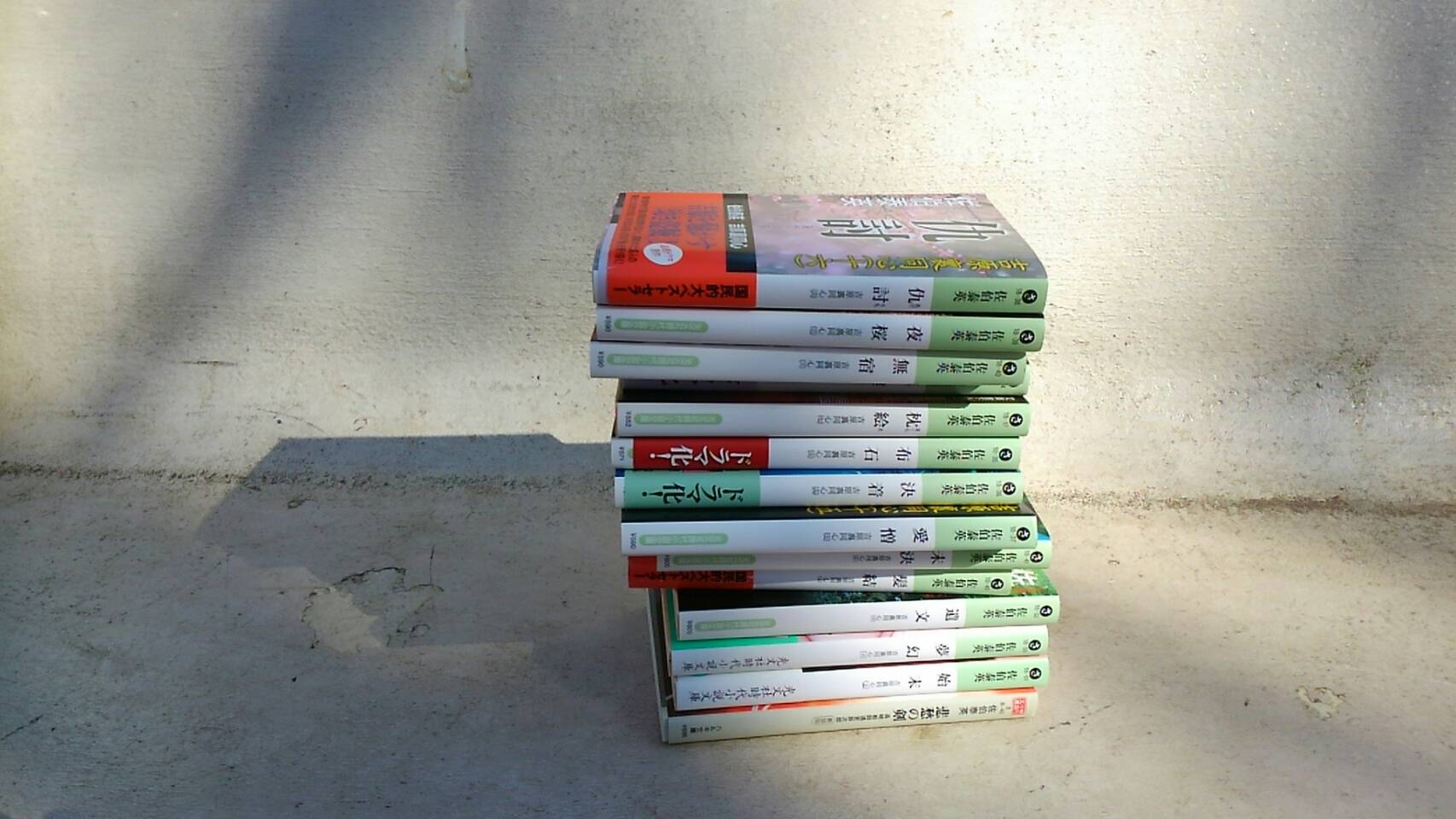
コメント